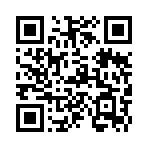この広告は365日以上更新がないブログに表示されます。
おかみ新聞20号の「中山製茶」のページで敬老の日の記載が
まちがっておりました。正しくは21日です。
訂正の上、その記事を下記に掲載いたします。
誠に申し訳ございませんでした。

風爽やかな季節を向かえました。皆様、いかがお過ごしでしょうか?
ハッピーマンデー法により、なんと今年は彼岸入りよりも後の
9月21日が敬老の日に
なります。
毎年15日だった頃を知る人にはなんだかちょっと変な感じですね。
さて、話は変わってこの新聞のタイトル「茶寿~ちゃじゅ~」ですが、
数えの108歳の賀寿のお祝のことです。「茶」の漢字の草冠を十と十に。
下の部分を八十八に分解します。そこで全てを足し算すると、
10+10+88=108になることから
こう呼ばれています。確かに数々の薬効を持つお茶を、
美味しく楽しみながら飲めば、まさに茶寿を迎えるまで健やかに過ごせそうな
気持ちになりますね。
大切なおじいちゃま、おばあちゃまに賀寿のお祝いをお送りしましょう。
まちがっておりました。正しくは21日です。
訂正の上、その記事を下記に掲載いたします。
誠に申し訳ございませんでした。

風爽やかな季節を向かえました。皆様、いかがお過ごしでしょうか?
ハッピーマンデー法により、なんと今年は彼岸入りよりも後の
9月21日が敬老の日に
なります。
毎年15日だった頃を知る人にはなんだかちょっと変な感じですね。
さて、話は変わってこの新聞のタイトル「茶寿~ちゃじゅ~」ですが、
数えの108歳の賀寿のお祝のことです。「茶」の漢字の草冠を十と十に。
下の部分を八十八に分解します。そこで全てを足し算すると、
10+10+88=108になることから
こう呼ばれています。確かに数々の薬効を持つお茶を、
美味しく楽しみながら飲めば、まさに茶寿を迎えるまで健やかに過ごせそうな
気持ちになりますね。
大切なおじいちゃま、おばあちゃまに賀寿のお祝いをお送りしましょう。
昨日から二日間のお祭り
たばた祭りへ



にぎやかに子供たちが遊んでいました
ほっとする夏のイベントです
たばた祭りへ
にぎやかに子供たちが遊んでいました
ほっとする夏のイベントです

今日と明日はたばたさん
夜店があります
 主人の小さいときはたくさん参道にお店が出たそうです
主人の小さいときはたくさん参道にお店が出たそうです
今は町内の人や膳所の方たちが守っておられます
この神社からおものの浜で船に乗せ、粟の御供(ごく)が運ばれていました
その由来から地名が膳所となりました
その粟の御供を象ったお菓子が
粟津の里です

神社にも2日間、供えられております
大津の夏祭りは中止になりましたが、
たばた祭はやっております
おこしやす
粟津神社の由来(大津市のHPより)
祭神は大国主命、大導寺田端介、田中恒世で、彦坐王(ひこいますおう)の創建と伝えています。膳所最古のお宮さんです。境内地は狭くお社も小さいのですが、膳所が粟津と呼ばれていた頃、西暦前に鎮座し膳所の総社でした。日吉大社山王祭には粟津神社からの粟の御膳を供えています。
夜店があります

今は町内の人や膳所の方たちが守っておられます
この神社からおものの浜で船に乗せ、粟の御供(ごく)が運ばれていました
その由来から地名が膳所となりました
その粟の御供を象ったお菓子が
粟津の里です
神社にも2日間、供えられております
大津の夏祭りは中止になりましたが、
たばた祭はやっております
おこしやす
粟津神社の由来(大津市のHPより)
祭神は大国主命、大導寺田端介、田中恒世で、彦坐王(ひこいますおう)の創建と伝えています。膳所最古のお宮さんです。境内地は狭くお社も小さいのですが、膳所が粟津と呼ばれていた頃、西暦前に鎮座し膳所の総社でした。日吉大社山王祭には粟津神社からの粟の御膳を供えています。